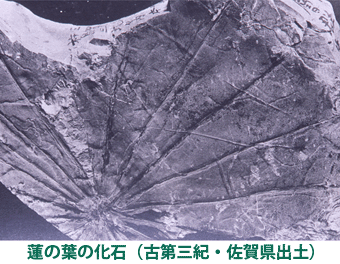| A B C D E F G H I J | |||||
�@�@�́A�A�����ނł́A��q�A����iAnthophyta)�̑o�q�t�A����(Discotyledonopside)�ɑ����Ă��܂��B���̒��ł��@�́A��r�I���������̔����I����A��P���N�O�ɂ͒n����ɏo�������Â��A���ł��B�@�̉��́A�k�A�����J�A�A���X�J�A���{�A���V�A�A�����A���[���b�p�ȂǁA���̂قƂ�ǂ��k�������甭������Ă��܂��B �@�@�̌��Y�n�ɂ��ẮA�G�W�v�g���A�C���h���A�������Ȃǂ���܂��B�����A��������ł���╨����������Ă��炸�A�܂�����̏�Ԃł��B �@�G�W�v�g���Y�n���́A���m�l�����@�Ƙ@�����������̂��A���������ԈႢ�̌��ł����B�Ñ�G�W�v�g�̈�Ղɕ`����Ă���̂͐��@�ł����āA�@�̉Ԃł͂���܂���B�G�W�v�g�w�ł������[�^�X�ilotus) �́A���@�̂��Ƃł��B�G�W�v�g�ɘ@�̉Ԃ��������܂ꂽ�̂́A������������̋I���O�V�O�O�`�R�O�O�N���Ƃ���Ă��܂��B�@�C���h���Y�n���́A�C���h�Ő��܂ꂽ�������A�@�̉ԂƐ[����������Ă��邩��Ǝv���܂��B�I���O�R�O�O�O�N�O�̃C���_�X�����̈�Ղ��甭�����ꂽ�n��_���̔����A�@�̉Ԃŏ����Ă��܂��B���̂��Ƃ�����A�C���h�ł��Â�����@�����炵�Ă������Ƃ�������܂��B |
|
||||
| �@�������Y�n���́A�����̐V�Ί펞��̉͛G�n�i���ڂƁj������Ղ���@�̉ԕ��̉����o�y���Ă��܂��B�������V�Ί펞��̑�@��(��������)������Ղ���́A�@�̉ʑ�̃f�U�C����������u���������@�v�i�ӂ��������j����������Ă��܂��B�܂��A�@���l���`���ꂽ�摜�A�i����������j�A����A���Ȃǂ̍l�È╨����������o�y���Ă��܂��B�ߔN�A�����]�Ȃ̊e�n�Ŗ쐶�@����������Ă��܂����A�܂����ߎ�ɂ͂Ȃ��Ă��܂���B �@���{�ł��@���������Ă������Ƃ́A��V�O�O�O���N�O����P���N�O�́u�@�̉��v���e�n�Ŕ�������Ă��邱�Ƃ�����ؖ�����܂��B�iZ�j |
|||||
|
|
|||||
| A B C D E F G H I J | |||||
�@���{�̘@�̉Ԃɂ́A�ꕔ�̒n�@�i�����A���̒n���ɐ�������@�j�������A�S�ĕi�햼�����Ă��܂��B�����A�u�Ñ�@�v����l�������āA�@�̉Ԃ̕i�햼�Ǝv���Ă��܂����A���́u�Ñ�@�v�Ƃ́A�܂��i�햼�����Ă��Ȃ����O���ڂ̉Ԃ̂��Ƃł��B �@�Ñ�@�Ƃ������O�́A���a30�N��܂ł͎g�p����Ă��܂���ł����B�@�̌����ɐs�͂��ꂽ����Y�����A��O�A�����E��A�s�ߍx�̕����X�Ŕ��@�����A��1000�N�O�̌Ø@�̎����J�Ԃ����A���̘@�̉Ԃ��t�����e���@�A�ʖ��𒆍��Ñ�@�ƌĂ̂��A�Ñ�@�Ƃ������O�̍ŏ��ł��B���̐}�ł̏��o�́A�k�����Y�E��{�S��̋����w�Ԙ@�x�i1972�N�j�ł��B �@����Y���͏��a26�N�A��t�s�ߍx�̌�����ŁA�@�̎����A��2000�N�O�̓D�Y�w���甭�����A���a28�N�ɊJ�Ԃ����܂����B�����͂�����u���N�@�v�ƌĂ�ł��܂����B��Ɂu���@�v�Ɩ�������āA�����ł́A�@�̉Ԃ̑㖼���̂悤�ɂȂ��Ă��܂��B �@�Ñ�@�Ƃ������O����ʉ�����̂́A��ʌ��s�c�s�ŁA���a48�N�A�S�~�ċp������ɁA�n���Ŗ����Ă����@�̎����@�B�ŏ������A���R���肵�č炢���̂���������Ă���ł��B |
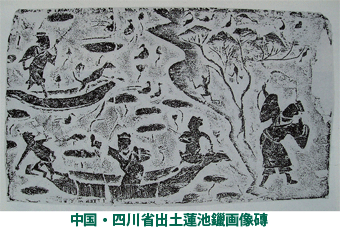 |
||||
| �@����͔N�㑪��̌��ʁA��1500�`2000�O�̘@�ł���Ɣ������܂����B�s�c�s�ł͂Ƃ��ɕi�햼�������A�u�s�c�̌Ñ�@�v�ƌĂ�ł��܂����B�Â��@������P���ɌÑ�@�ƌĂ��̂Ǝv���܂��B �@���̌�A�s�c�s�ł͓V�R�L�O���Ɏw�肵�āA�����ۑ����邽�߂ɘ@�������A1995�N�Ɉꕔ���J�����A2001�N�S���ɂ́u�Ñ�@�̗��v�Ƃ��ďv�H���܂����B���̊J���ɍ����āu�Ñ�@�v�ɂӂ��킵�����O���s�������W���܂����B �@���̌��ʁA���O���ڂ̘@�́u�s�c�@�v�Ɍ��܂�܂����B���̊ԁA�l�Êw�u�[���Ƃ��d�Ȃ��āA�Ñ�@�₻�̘b�肪�S���ɓ`����āA�i�햼�Ǝv���悤�ɂȂ����̂ł��B�iZ�j |
|||||
|
|
|||||
| A B C D E F G H I J | |||||
�@�@�̉Ԃɉ���ނ��̐F�����邱�Ƃ��L�����ŏ��̏����́A�C���h�Ő��܂ꂽ�����̏����̕��T�ł���A���̂悤�Ș@�Ȃ������@���ڂ��Ă��܂��B �@utpara,uppala�i���炫���@�j �@kumuda�i��炫�����@�j �@padoma�i�Ԃ��@�j �@pundarika�i�����@�j �@��L�̘@�Ȃ������@�����鎞�A���ʂ̂ق��ɁA���ՂȈӖ�������Ȃ������߁A�d��Ȍ�����܂����B �@�܂��������Ƃ��Ȃ��Ԃ̐F���A������̂Ǝv���ĖĂ��܂�������ł��B���̎l���A�����ɋ�S���āAutpara��@�Akumuda�����@�Apadoma��ԁi�g�j�@�Apundarika�𔒘@�ƁA���ꂼ��ɁA�F�Ŗ����ɋ�ʂ��܂����B �@�����C���h�ƒ����ɂ́A�g�@�Ɣ��@���������Ă��܂������A�@�Ɖ��@�͐������Ă��Ȃ������͂��ł��B�@�͂܂���������Ă��܂��A�A�����J�Y��̉��@����{�l���ŏ��Ɍ����̂�20���I�ɓ����Ă���ł��B�@ |
 |
||||
| �@ �@�ɂ́A�g�F�E���F�̉Ԃ��炩���铌�m�Y��iNelumbo nucifera)�ƁA���F�̉Ԃ��炩����A�����J�Y��iNelumbo lutea)�̂Q��ނ�����܂��B����瓌�m�Y�ƃA�����J�Y�̘@�́A�n����ɒa�������������������ɕʂꂽ���̂Ǝv���܂��B �@���̍g�@�E���@�ƁA���@�Ƃ́A�Ԃ̐F���قȂ邾���ŁA�`�Ԃ���F�̂̐��͓����ł��B�ł�����A�݂��Ɍ��G���ĐV�i�����邱�Ƃ��o���܂��B�@�@ �@���āA���n�̘@�̉Ԃ͂ǂ�ȐF���������Ɛ\���܂��ƁA�g�F���Ǝv���܂��B���̍g�@�̉ԕق̂����ꕔ���A�܂�ɓˑR�ψقŔ��F�ɕς�邱�Ƃ�����܂��B �@���n�̘@�̉ԐF���A�g�@����A�A�W�A�ł͔��@���A�A�����J�ł͉��@���ˑR�ψقŐ��܂ꂽ�悤�ł��B�������A�a��������͎c�O�Ȃ���s���ł��B�iZ�j |
|||||
|
|
|||||
| A B C D E F G H I J | |||||
�@�@�́A�Ԃ��Ϗ܂���Ϗܘ@�A�@�������n����H�p�@�ɑ�ʂ���܂��B�܂��A�@�̎������n����i�������A�ߔN�A�����ł͑���@�Ȃǂ���o����Ă��܂��B�����ł́A�Ϗܘ@�̕i��ɂ��Ă̂L���܂��B �@�@���͔|����ɂ͍L���r�����z�ł����A�قƂ�ǂ̐l�͕i��ۑ��ƍ͔|�ꏊ�̊W�Łu���A���v�ň琬���Ă��܂��B�@�̉Ԃ͍͔|�����ɂ���āA�Ԃ̍炭�����A�Ԍa�A�s�̏�A�t�̑傫���A�ԕق̐F�Ȃǂ����Ȃ�Ⴄ���Ƃ�����܂��B���̉Ԍa�̑召�A�ԕق̐F�A�ԕق̐��ɂ���ĕ��ނ��܂��B �@�Ԍa�̑召�ł́A��`��i�Ԍa��26�p�ȏ�j�A���ʎ�i�Ԍa��25�p�`16�p�j�A���^��i���q�@�E�Ԍa��15�p�`�X�p�j�A�q�@�i�Ԍa���W�p�ȉ��j�ɕ����܂��B�@�@�@�ԕق̐��ł́A��d�i�ԕِ���25���ȉ��j�A�����d�i�ԕِ���25�`50���j�A���d�i�ԕِ���50���ȏ�j�ŁA�ȂǂƂȂ�܂��B �@�ԕق̐F�ł́A���@�n���i�ԕّS�̂����j�A�g�@�n���i�ԕّS�̂��g�j�A���@�n���i�ԕّS�̂����F�j�A���@�n���i�ԕقɎ��g�F�̔�������j�A�܍g�n���i�ԕق̐�[�≏�ɍg�F�j�A���g�@�n���i�W�����F�̉ԕق̐�[�≏�ɍg������j�A�ɕ��ނ��Ă��܂��B |
 |
||||
| �@���q���Y���w�Ԙ@�S�x�i2002�N�j�ɂ́A�̓��c���v�������W���������i������j�r�̘@����ɁA�P�U�W�i��̎ʐ^���f�ڂ���Ă��܂��B �@�����̉����� �E���s���� �w�����ԕi��}�u�x�i2005�N�j�ɂ́A 608�i��̎ʐ^���f�ڂ���Ă��܂��B �@�킪���ł��V�i��̍�o������ɍs�Ȃ��Ă��܂����A�S�̑��͂킩��܂���B�e�n�ł̌ď̂ɏ]���A�ݗ����150����A�ߔN��o���ꂽ�i���������ƁA�����Ɠ��{�������Ė� 900�i��ȏ゠�肻���ł��B�@ �@�Ȃ��A��ԑ����i��͈�d�̍g�F�A������d�̔��ł��B���d�̉��F��A���d�̔���͕i�킪���܂肠��܂���B�iZ�j |
|||||
|
|
|||||
| A B C D E F G H I J | |||||
�@�@�Ɛ��@�͋ߔN�܂ŁA�������ԗe�����Ă���Ƃ��납��A���������A���̒��Ԃƍl�����A���@�Ȃɑ����Ă��܂����B �@�������A�ߔN�̖ڊo�܂����Ȋw�̐i���ŁA�c�m�`����z��A�~�g�R���h���A��`�q�A���F�̈�`�q�A�ԕ��\���Ȃǂ̌����̌��ʁA�@�Ɛ��@�͏]���l �����Ă����i���Ƃ́A�܂�����������i�������Ă������Ƃ��킩��܂����B �@�����̌����ɂ��ƁA���@�͔�q�A���̒a���̏����ɕ��������u�Ñ��{�Q�v�ɓ���A�@�͔�r�I��ɕ��������u�^���o�q�t�A���v�ɓ���܂��B���̈Ⴂ�͉ԕ��̌`�Ԃɂ悭������Ă��܂��B �@�Ñ��{�Q�̐��@�́A����a���ԕ��̎�����Ƃ�܂�������a�����Ă��܂����A�^���o�q�t�A���̘@�́A�O�̔���a����Ȃ�O�a���̉ԕ��������Ă��܂��B�@�@�Ɛ��@���ԕ���z���Ă��ł��܂���B �@�ŐV�̐A�����ފw�ŁA�@�͘@�ȁiNelumbonaceae) �A�@��(Nelumbo)�ł���A���@�́A���@�ȁiNymphaea-ceae�j�A���@���iNymphaea�j�ɑ����܂��B���҂͂܂������قȂ�A���ɕ��ނ� |
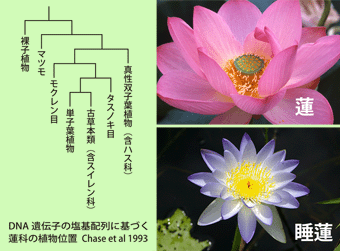 |
||||
| ��Ă��܂��B�����A�����̏����͂��܂��ɁA���@�ȁE�@���Ƃ����������̗p���Ă��Ďc�O�ł��B �@�Ƃ���ŁA�@�Ɛ��@�̊ȒP�Ȍ�������������܂��B�@�͉Ԃ̒����Ɏ��ǂ������Ă���ԑ����܂����A���@�ɂ͉ԑ����܂���B�@�̉ԕق͂ӂ����炵�ĕ����L���ł����A���@�̉ԕق͍ג����ԕق̐�[���s�p�I�ł��B �@�܂��A�@�̗t�͊ۂ��ł����A���@�̗t�ɂ͐[���ꍞ�݂�����܂��B�@�̒n���s�͐H�p�̃����R���ɂȂ�܂����A���@�ɂ̓����R�����o���܂���B �@�ԐF�ł͐����@�͂���܂����A���@�͂܂���������Ă��܂���B�iZ�j |
|||||
|
|
|||||
| A B C D E F G H I J | |||||
�@�쐶�̘@�Ƃ́A�l�Ԃ��Ǘ����邱�ƂȂ��A�厩�R�̂Ȃ��Ŏ���̐����͂ɂ��A���炵�Ă���@�̂��Ƃł��B �@���̒n���ł́A�@���ӂ��ސA���́A�l�Ԃ��ӂ��ޓ��������A�͂邩�ɐ�y�i�ł��B ���̏؋��ɂ́A�@�̉��i�t����Ȃǁj���A���[���V�A�嗤��k�A�����J�嗤����o�y���Ă��܂��B�����̉��́A������V�O�O�O���N�`�P���N�ȏ���O�̂��̂ł��B�l�ނ̗��j�͂��������V�O�O���N�ł��傤�B�@��S�U���N�Ƃ����n���̗��j�ɂ́A�S��̕X�͊���ΎR�̑啬�A覐̏Փ˂Ȃǂ�����܂����B�����������ł��A�@�͐�����Â��Ă��܂����B �@�����ŋ߂Ɋm�F����A�ʐ^�̂���쐶�̘@���R�����Љ�܂��B �@�k�āA�t�r�`�E�C�X�R���V���B�|�[�e�W�́A�~�V�V�b�s�[�̍ŏ㗬�ɂ�����܂��B�Ώ��Ɣ��A����ɖq���n�ŁA�قƂ�ǖ��l�� |
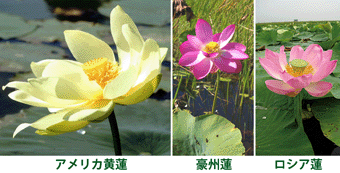 |
||||
| �ꏊ�ł��B�����̃}�b�h�i�D�j�ɁA�Q������A�����J���@������܂����i���j�B �@�I�[�X�g�����A�嗤�̖k�������A�J�J�h�D���������̎��n�тɂ́A�Ԍn�̖쐶�@�����炵�i���j�A��Z���̃A�{���W�j�́A���̘@�̍������H�p�A��p�ɂ��邻���ł��B �@�A�W�A�嗤�̓��k���A���V�A�ƒ����̍������Ȃ��A���[����i�����]�j�̒�����i�k�܂S�W�x�I�j�ɁA�s���N�F�̖쐶�̘@�����炵�Ă��܂��B�����ŋ߁A���V�A�ƒ����̌����҂ɂ��m�F����܂����i�E�j�B�iG�j |
|||||
|
|
|||||
| A B C D E F G H I J | |||||
�@�Ԙ@�Ƃ����̂́A�@�̉Ԃ̂��Ƃł͂���܂���B�Ԃ��炩����@���A�킴�킴�Ԙ@�Ƃ����̂ɂ́A����Ȃ�̗��R������܂��B �@�l�Ԃ��@�ɊS���������̂́A��ɂ��̍��̕����ł����B�����R���i�������́A���ł͂Ȃ��A�n���s�j�ł��B�H�ނƂ��āA�ݑ܂̗v���������߂ɁA���ڂ����̂ł����B�������R�O�O�O�N�O�A�����l�͖�40��ނ̐A����H�ׂĂ��܂����B���̂R���̂Q���̏W���A�����R�����ӂ��ނR���̂P�͒��x�̍���������A�͔|���Ă��܂����B���Ȃ݂ɒ�����ł́A�@���ׁi�z�[�j�A�����R�����X�i�I�E�j�Ƌ�ʂ��Ă��܂��B �@�@�̎����܂��A�����R���ȏ�Ƀf���v���Ȃljh�{�f�̌ł܂�ł���A���}����܂��B �@���̒��S�ɂ���ΐF�̕����́A���i�͂����j�ŁA�����͂�������n�܂�܂��B���̕����͂ƂĂ��ꂭ�A������ɂ��Ȃ�܂��B�����̍]���ȍL���̂悤�ɁA���ォ�����ړI�Ƃ��Ę@��A�� |
 |
||||
| ��Y�n������܂��B �@���̖ړI�������R���ł���A���ł���A�@�ɂ́A�������Ԃ��炫�܂��B������Ϗ܂���̂��Ϙ@�i������j�ł��B���̊Ϙ@�����y�������邽�߂ɁA��������Ԃ��炩����@���A�Ƃ��ɉԘ@�ƌĂԂ悤�ɂȂ�܂����B�V�������t�ł��B���{�ł́A�P�X�V�O�N�キ�炢����ŁA�������p��ɂ͂܂�����ɑ�������\�����Ȃ��悤�ł��B �@�ԃV���E�u��ԃJ�^�o�~�̂悤�ɁA�Ԙ@��������u�s�����v�邱�Ƃł��傤�B�iG�j |
|||||
|
|
|||||
| A B C D E F G H I J | |||||
�@�@�́A�L������n���s���痧�t��Ԃ��o���܂��B���̐�[����A���̔�債���n���s���u�@���v�Ƃ����܂��B �@�@����A���܂��ƁA�i��̓��ꐫ�i�����`�q�j��ێ����邱�Ƃ��ł��܂��B �@�@���A�����݂̎��G �@�C����15���ȏ�ɂȂ�Ɖ肪�L�т܂����A15���ȉ��ɉ�����Ɛ������~�܂�܂��B����10cm���s�̐L�т���Q���A�~�J���Ɍ͂��̂����ׂ̈ł��B�@���̐A�����݂́A�O�C�����肷����O���̌o�߈ȍ~�A�t�̖G����O��ڏ��ɂ���Ɨ�Q��������܂��B �i�C�ے�DATA http://www.data.kishou.go.jp/etrn/�j�@ �@�@���̌@��o���Ɛ藣���� �@�܂�A���t���A�茇���ɒ��ӂ��@��o���܂��B�L���n���s���番���@���́A�����s���^�ɕt���Đ�o���Ă��������B �@�y�̗p���� �@�c�y�A���y�A���y���̕��s�L�̂Ȃ��y��I�сA�I��S�~���������ׂ����ق����p���܂��B |
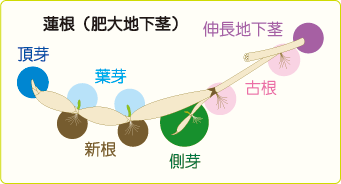 |
||||
| �@�엿�̗^���� �@���fN�A�ӎ_P�A�J��K���̗{��������Ƃ��ĕK�{�ł��B�L�@�엿�͊��S���y�̂��̂��B�ǔ�͔������Ƃ�5-5-5�n�̂��̂����ʁi�y�A�����킹50���b�g���ɑ�10g���j�^����B�^���߂���Ɨt�Ɉُ킪������̂ŁA�������ւ��Ĕ��߁A�K�ʂ�͂ޕK�v������܂��B �@�A���� �@���^��ȊO�̕i��́A�ی^�̌��̖����i�����͍Œ�30cm�K�v�j�e��ɁA������������y������2/3������A�y�̔������̐[���ɐA�����݂܂��B�i����𐅕����A��≺�����ɂ���j����1/3���炢�̍����ɒ���A�펞�͂炵�Ă͂Ȃ�܂���B�iT�j ���@�p�z���̌���A�ǔ삪�̔�����Ă��܂��B �i���j�����엿 TEL 0476-92-1108 |
|||||
|
|
|||||
| A B C D E F G H I J | |||||
�@���̔��菈�����G�A�C�� �@�@�����S�����{�ɔ��菈�����A���x�i15���ȏ�j�ƌ��i�d���ł��ǂ��j���m�ۂ��Đ��������A�T��������U�����{���ɂ����Ĕ����ɐA���ւ��܂��ƁA�X�����܂łɂ͊J�Ԃ��\�ł��B �@����̂����� �@�@���͂P�o�����̌ł��O���ɕ���ꂢ�Ă܂��B���ɐZ���Ƃ��ꂪ�ӂ₯�܂����A���藦�͋ɒ[�ɒႢ�̂ł��B�O���̈ꕔ�i�`���j�������e��̐��ɐZ���ƁA�c�����̍�������̋z���ŊO��炪����A������c��ݓ�ɊJ���܂��B���̂悤�ɔ��菈��������ƁA��̔��藦�͔���I�ɍ��܂�܂��B �@�O���̌������i���菈�����@�j �@���̊O��炪�͂��ɐ���オ���`���̒��S�ɂ͐ꖡ�̗ǂ����^�j�b�p�[�i�œK�̐n���j����ɏ������Ȃ��悤���`�� |
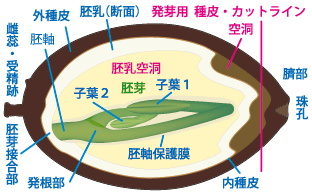 |
||||
| �i�}�Q�Ɓj�����܂��B �@��̐����ƐA�����ݕ��@ �@���菈����A����10cm�ȏ�̐����ɔ��菈���������߂Ă����ƁA�C����������i15���ȏ�)�S�A�T���ڍ��ɂ͔�����m�F�o���܂��B�Ȍ�A���̏o�n�߂鍠�܂łɔ����ɐA�����݂܂��傤�B �@�@���蔭�肳���āA�@�̉Ԃ��炩���邱�Ƃ��o���܂����A�e�Ƃ͈قȂ����i��ƂȂ�܂��B�iT�j |
|||||
|
|
|||||
| A B C D E F G H I J | |||||
�@�悭�u�@�Ɛ��@�̈Ⴂ�v�̐����ŁA�t�����ʂɕ�����ł���̂��u���@�v�ŁA���ʂ��痧������Ă���̂��u�@�v���Ƃ���܂��B����͂��������ł��B �@�Ȃ��Ȃ�A�@�ɂ��A���ʂɕ����ԗt�����邩��ł��B�t�A���N�܂łɐ��������@���̐�[�̉肩��o��t�́A���ʂɕ����т܂��B������u�����t�v�ƌĂ�ł��܂��B �@�Q�`�R�����ʂɕ����ԗt���o����A�V�������s����o��t�́A�l�q���قȂ�܂��B�����t�����t���i�悤�ւ��j�������A�\�ʂ��d���g�D�ɕω�����t�Ȃ̂ł��B������u�����t�v�ƌĂ�ł��܂��B �@���̗t�͐��ʂ���o�Ă��鎞�́A���E��������ɂ�����Ɗ�������ԂŁA�t���ɑ��Ď߂̏�Ԃł��B���̌`����u�V�����N�i���j�t�v�ƌĂ�܂��B�����t�̐����́A��i���ˁj�@���̒����{���ł܂��Ȃ��܂����A�ԉ�����킹�����t���`�������ł��A�厖�Ɉ�Ă邱�Ƃ��ǂ��ƌ����Ă��܂��B �@��q���甭�肳�����ꍇ�́A�܂��������ꂽ�c�肩��R���ȏ�̕����t���ł܂��B���̌�A�V�������s���L�� �ĉh�{��Ԃ������Ă͂��߂āA���t�ƂȂ��ĉԂ��炭�̂ł����A�`�ԓI�ɂ́u�����t�v�̏�Ԃ̂��Ƃ�����܂��B |
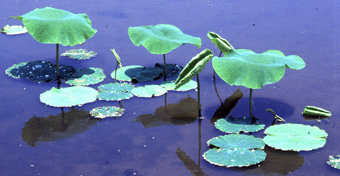 |
||||
| �@�u�����t�v���o�Ă��鎞�A�t�̐F���Ԗ���ттĂ���̂́A������������c�t����邽�߂��ƁA�����Ă��܂��B �@�@�̗t�ɂ���C�E�͂قƂ�Ǘt�̏�ʂɍ݂�܂��B�����t�����t�������ł��B �@��\���{����t�����W�܂��������̉ו@�i���сj�́A�t������n���s�ւƂȂ����Ă��܂��B������ʂ�A�_�f�́A�n���s�̐ߕ��ɂ��鍪�̍זE�܂ŋ�������܂��B �@�C�E�́A���łɏq�ׂ��悤�ɁA�t�̏�ʂɂ���܂��B���[�̐[���Ƃ���Ő��炵�Ă���@���A����Ȃ�ɗt����L���ēK�����Ă��܂��B�܂��A�^���Ȃǂŋ}�ɑ����������́A��ӂɐ��\�Z���`���L�����đΉ����邻���ł��B�Z���Ԃɐ��������ƁA�_�炩���s���t�̏d�݂Ő܂�Ă��܂��A�͎����邱�Ƃ����邻���ł��B �@���Ĉɓ����i�{�錧�j�̘@���䕗�ɂ�鑝���Ő��v���āA��Ō������������Ƃ�����܂����B���ɐ�����@�ł����A�����ɁA���Ɏア��ʂ��������Ă���̂ł��B�iK�j |
|||||